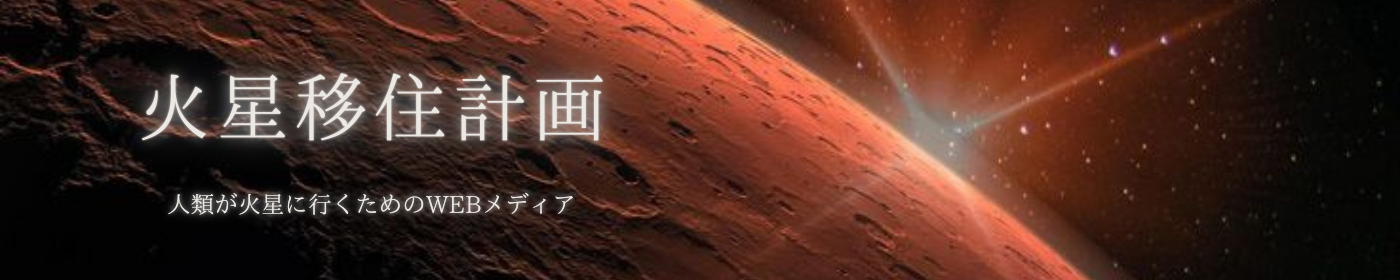宇宙空間を活用したインターネットサービスといえば、イーロン・マスク氏率いるSpaceXのStarlinkが最前線を走っています。しかし、実は我が国日本にも、独自の衛星ネットワークが存在することをご存じでしょうか?
先日、MWC Barcelona 2025にて、NTTグループが展開する宇宙ビジネスブランド「NTT C89」の取材機会を得ました。今回は、その革新的な取り組みについてご紹介したいと思います。

3種の衛星が織りなす、多層的なネットワーク
NTT C89は、既に実用段階に入っている衛星インターネット接続サービスです。その中核を担うのは、GEO、LEO、HAPSという3種類の衛星。これらが連携することで、電波の届きにくいエリアをカバーしつつ、地球表面の精密なデジタルツインを生成しているのです。
デジタルツインは、研究や災害シミュレーションの精度を飛躍的に向上させ、災害対策や資源の効率的な活用など、多岐にわたる分野での応用が期待されています。それぞれの衛星の役割を詳しく見ていきましょう。
- GEO衛星(静止軌道衛星):地上にいるスマートフォンなどとの通信を担い、災害時や離島において基地局としての役割を果たします。4G・5Gにも対応し、ドコモの「ワイドスターⅢ」を通じて利用可能です。
- LEO衛星(低軌道衛星):地球観測と通信の2つの機能を有しています。観測衛星は地表をスキャンしてデジタルツインを生成し、通信衛星はHAPSよりも広範囲なエリアをカバーします。また、IoTデバイスとの接続も可能です。
- HAPS(高高度プラットフォームステーション):成層圏を飛行する無人航空機で、通信環境が整っていない地域に通信を提供します。地上約20kmの上空を数日間から数ヶ月間、無着陸で飛行し、直径100~200kmのエリアをカバーすることが可能です。これにより、従来は通信エリア化が困難だった空や海上、過疎地域などでも通信が可能になります。
Starlinkとの連携、そして独自の強み

GEOとLEOは既に運用が開始されており、LEOはStarlinkとの連携も視野に入れています。HAPSは2026年の商用化を目指し、現在ケニアで実証実験が行われています。
NTT C89の強みは、単なる通信手段の提供にとどまらず、地球の地形をスキャンして災害情報を収集するなど、日本国内でのニーズに応える多機能性にあります。89番目の新たな星座として、私たちの生活に欠かせない存在となる日は、そう遠くないかもしれません。